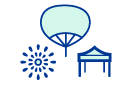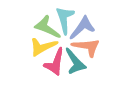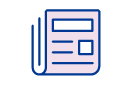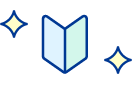<豊田>一度見たらクセになる! 華やかに、力強く。心躍る挙母祭り
掲載日:2020年5月3日(日)
【開催日】毎年10月第3日曜日とその前日 2023年は10月14日(土)・15日(日)
【開催場所】下町地区、樹木地区、挙母神社、城跡門、豊信本店前交差点、豊田市駅前、矢作川河川敷
~祭り観覧にお越しになる皆さまへ~
祭り当日は、複数のイベント開催に伴い、中心市街地及び周辺道路・駐車場における混雑が予想されます。お時間に余裕をもって各イベントにお越しいただくとともに、公共交通機関のご利用にご協力ください。
一度観ると「また来年も観に行きたい!」とクセになってしまうのが、挙母祭り(ころもまつり)。何がそんなに強く惹きつけられるのか、挙母祭り保存会事務局長の那須与一さんにその魅力についてお伺いしました。
―挙母祭りの歴史について教えてください。
挙母祭りのあるこの地は、「挙母藩」のあったところ。慶長9年(1604年)に、三宅氏が挙母城に入封して以来、挙母はつねに豊田の中心でした(ちなみに「豊田市」になる前は「挙母市」)。
そんな城下の祭りであった「挙母祭り」は寛永年間(1624年〜1643年)頃にはじまったと言われています。当初は大八車を飾りつけた程度のものだったそうですが、安永7年(1778年)には現在のように8台の山車が登場していました。
明治初期に川上呉山によって描かれたという蒔絵には、挙母神社や挙母城に曳き入れられた8台の山車の前で各町の子どもたちが「歌舞伎狂言」を披露し、それを藩主・家臣たちが観ている様子が描かれています。
※豊田市郷土資料館 所蔵
―歴史ある祭りなのですね!
そうです。伊勢神宮の神嘗祭(五穀豊穣を感謝する神事)が10月16・17日。伊勢神宮と縁の深い挙母神社ではその後の18・19日に祭りを行っていたのですが、最近では仕事が休みになる土日に行われますね。
―伊勢神宮とは意外でした。
土曜日の試楽(しんがく)で、19時より「七度参り」が行われますが、こちらも神嘗祭同様、五穀豊穣祈願のため、境内を七周する神事です。子どもたちは、竹にくくりつけた赤いほおずき提灯を持って歩き、とても風情があるものですね。3周すると子どもは抜け、大人が行うのですが…この時は、オイサオイサともみ合うのです。雰囲気がガラッと変わるので面白いと思いますよ。夜の縁日の雰囲気も楽しめますしね。
―それにしても素晴らしい山車ですね。
そうですね。一番上の部分を見てください。他所ではここでからくりを行い、柱が4本です。ところが、挙母ではここに人間が乗るため6本の柱になっています。また、山車に繋がるように4畳ほどの板張の舞台を作り、ここで子どもたちが三河歌舞伎を披露するんです。愛知には多くの山車がありますが、その中でも異色の山車ではないでしょうか。
―挙母祭りで印象的なのが大量の「紙吹雪」。これはどうしてはじまったのですか?
明治初期に山車の順番を巡り騒動となったため、1番最初の車を「華車(はなぐるま)」と呼び、いつの頃からかくす玉や特別な飾りをするようになり、これらと共に紙吹雪をまいて特別な演出をするようになったのがはじまりです。清めの塩ってあるでしょう?それと同じように、山車から神の御加護を、ということで紙をまくという…。
僕の幼い頃は、紙吹雪はチラシを切って作っていましたが、最近では短冊型のカラフルな紙吹雪をまいています。短冊だとひらひらと舞いながら落ちるのでキレイでしょ。紙質もまき方も試行錯誤しながら、より美しく見える演出をしています。
例えば中町では、印刷された紙吹雪もあるんです。それを地面に落ちる前にキャッチして、お財布に入れると金運がUPするということで、多くの方がご加護を求めて手を伸ばします。
―この時はいちだんと大歓声が沸きますね。
そうなんです。こちらもまくときは興奮します。祭りを続けていくのは大変なことですが、この日、観ている方たちからの大きなどよめきや拍手があるからこそ、僕たちも祭りの楽しさを強く感じますし、これからも続けていきたいと思うんです。
―挙母祭りらしい見どころというと、日曜日の10時ごろから挙母神社で行われる「曳き込み」から16時からの「曳き出し」ですね。
挙母の山車は、後ろにしか梶棒がなく小回りでは周れない構造になっています。それをあえて、勢いよく、小回りで周すのですから、相当な技術が必要だと思います。こればかりは、うまく言葉では表せないような綱と梶の「間」があるんですよ。
―パパパパーンという号砲を合図に、一輌ずつ境内へ駆け込んでいく「曳き込み」、勢いよく大楠前を曲がり、境内を後にする「曳き出し」、どちらも祭りならではの人々のパワーを感じますね。
そうですね。人の力はすごいです。梶方は祭りの翌日は肩が腫れあがりますから(笑)。そこまでの力が出てしまうのも祭りがなせる不思議な力じゃないでしょうか。
この後は「泣き別れ」。挙母神社を曵き出された山車は、豊田信用金庫本店前の交差点で、上町三町は南に、下町四町は北に、それぞれ帰っていくのですが、華車より、無事催行の挨拶と、次年の華車の町への申し送りをします。
そして18時半からは奉納花火が打ちあがり、祭りの終わりを告げるのです。
おいでんの花火大会ほどじゃないけど、結構大きな花火が打ちあがりますよ。花火の音を聴くと「ああ今年も無事に終わった」としみじみ思うんです。