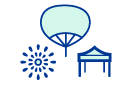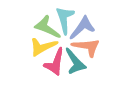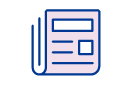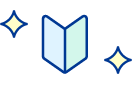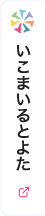結果一覧

このマークのあるイベントはいこまるが貯まるイベントです。
「いこまいる」とは?


豊田の様々なスポットに出かけたり、イベントやスタンプラリーに参加することで、クーポンや特産品に交換できる観光サービスです。
豊田のお出かけがもっと楽しくなるサービスなので、ぜひご登録ください。
-
小原
白鳥神社
西暦807年、大同2年建立の古い神社。 日本武尊が東夷を征伐した帰りに立ち寄られ、数日ここにとどまって二本の木を植えて立ち去られました。 お手植えされた二本の木にちなんで『にぎ』という地名になりました。
-
小原
市場城跡(大草城跡)
市場城は、標高380mの山頂にある室町時代の山城です。 文亀二年(1502)に初代鱸(鈴木)紀伊守親信が築いてから、文禄元年(1592)に退去するまで90年間、鱸氏の居城でした。(第二代 肥後守長重、第三代 伊賀守直重、第四代 越中守重愛) 現在見られる城の遺構は、四代城主重愛が串原、広瀬の城を攻めて大功をたて、天正十一年(1583)家康から所領の加増を受けたときに改修したものといわれています。改修には鉄砲の登場による戦法の変化や当時の築城技術の発...
-
小原
蚕霊神社
愛知高原国定公園内にあり、蚕をお祀りしている神社として知られ、「こだまさん」と呼ばれ親しまれています。小原地区内唯一の宗派神道の社で、当初、御嶽大名神が祀られ、江戸時代から相当の信者がありました。 明治20年小原村一円に伝染病が流行し、伊勢神宮外宮より大気都比売命を勧請して蚕霊神社の建立が図られました。 縁結びの神様としても有名です。 ※道路幅が狭い区間ありますので、ご注意ください。
-
小原
嶺雲寺
市場城の家来の菩提寺として1535年に建立されました。本尊は聖観世音菩薩像で、右側には男碑像、左側に女碑像が鎮座。また、本堂左側には羅漢像が祀られています。山門近くには、樹齢400年以上のしだれ桜もあり、春の桜、夏の新緑、秋の紅葉と四季それぞれの彩りを添えてくれます。
-
小原
家康の腰掛石
江戸時代の頃、徳川家康公が小原一円の様子を視察に来たときに床几として石の上に座ったと伝えられています。 小原町の賀茂原神社に大人で一抱えほどもある石(150kg)があり、 そのそばに『御腰掛け石」と刻まれた標柱が建っています。 「力石」とも言われています。
-
小原
星の宮神社
昔、この地に星が落ちてきたので、そこに社を建て、それを祀って「星の宮」と呼ぶようになりました。 ご神体は隕石であるといわれています。雷が2回ほど神社に落ち、神社に雷が落ちると言う事は神が降りてきて縁起が良いとされています。 不思議なパワーのある神社です。 ※駐車場はありません。
-
小原
和紙工芸体験館
小原和紙は、植物の繊維を染色したものを絵の具がわりにして、紙をすきながら絵を描く、小原地区特有の美術工芸。 この小原和紙工芸の魅力を伝える工房が、和紙工芸体験館です。ここでは「絵すき」「字すき」「葉すき」「うちわ」「壁掛け」を制作できます。また、小原和紙工芸講座を開催しており、本格的に小原和紙工芸に取り組むことができます。
-
小原
小原和紙美術館
豊田市小原和紙のふるさとは、手つかずの自然が残る山林にあります。小原工芸和紙の魅力を伝える美術館「小原和紙美術館」があり、藤井達吉の美術工芸作品の展示などが楽しめます。春には和紙の原料となるミツマタ、秋には四季桜が美しく、山々を華やかに彩ります。
-
下山
大桑城跡
15~16世紀に巴川と大桑川の合流地点の高所に築城された山城で、城主は川合弥十郎と伝えられています。城主は平時には麓の居館に過ごし、戦時にはこの城で指揮を執っていたと思われます。戦国時代に大桑城の周辺は甲斐の武田氏が三河や遠江に進出する為に、城郭の攻防が行われていました。「東照軍鑑」には1550年に駿河の今川義元に従わない者の中に、川合弥十郎の名前が記述されています。1565年に徳川家康が大沼、田代へ出陣した際に川合弥十郎を引き付けて帰陣したと...