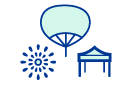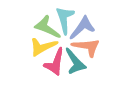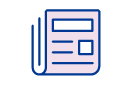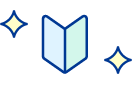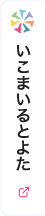結果一覧

このマークのあるイベントはいこまるが貯まるイベントです。
「いこまいる」とは?


豊田の様々なスポットに出かけたり、イベントやスタンプラリーに参加することで、クーポンや特産品に交換できる観光サービスです。
豊田のお出かけがもっと楽しくなるサービスなので、ぜひご登録ください。
-
足助
観音山
第二の香嵐渓とも呼ばれる、もみじの名所。山頂付近には観音寺があり、木造天部立像は豊田市指定文化財になっています。
-
足助
ZiZi工房
足助のおじいさん&おばあさんたちが、真心こめてハムやウィンナーを作っているのが、「足助ハム ZiZi工房」です。 人のぬくもりがスパイスだと、厳選された素材を使い、手作りの商品は美味しいと好評で、今や、足助を代表する名物商品になっています。ZiZi工房は、レストランや日帰り入浴、介護施設も兼ね備えた「百年草」の中にあります。 店では、焼きたてのフランクフルトを食べることができ、試食もOK!
-
足助
飯盛山
愛知130の山にも選定されている香嵐渓の飯盛山。平安時代の終わりごろに足助家初代・重長が飯盛山城を築きました。 北西向き斜面の約0.5haにカタクリの群生地があり、4月上旬まで見られます。 3月中旬頃に暖かい日に一気に開花し、天気の悪い日や、夜には花を閉じてしまいます。
-
足助
三州足助屋敷
生きた民俗資料館と言われる三州足助屋敷は、かつての豪農屋敷を再現し、昭和55年に開館しました。 ここでは、かつてこの地域で行われていた「炭焼き」「木地」「機織り」など、暮らしの“手仕事”が行われています。手仕事の中には、体験できるものもあります。
-
足助
弘化2年の道しるべ
中馬街道と遠州街道の分岐にある道標。「ぜんこう寺(善光寺)」「ほうらい寺(鳳来寺)」と彫られています。
-
足助
寧比曽岳
愛知県の北東部に位置する寧比曽岳(標高1121m)は、伊勢神方面の恵那コースと、足助方面の本線コースの2方向に分岐しています。山頂からの眺望もよく、1年を通して親しまれています。東海自然歩道なので登山道は登りやすく、ベンチもたくさん整備されているのでゆったり登山したい方に最適です。
-
足助
重要文化財 旧鈴木家住宅(紙屋鈴木家)
国指定重要文化財「旧鈴木家住宅」は、約4,000㎡の敷地に16棟の建物が建ち並ぶ、江戸時代から続いた大商家の屋敷です。 屋号を「紙屋」といい、紙、漆、醸造業や金融業、土地経営で財を成し、江戸から明治にかけて足助の経済や文化を牽引してきました。 令和5年8月から主屋の公開が始まり、当時の建物の様子を見て感じることができます。 主屋の奥では残り15棟の保存修理工事が引き続き行われており、工事の様子を見学できる特別ツアーも行われています。
-
足助
大鷲院
大鷲院は、足助にある霊場。山岡鉄舟の筆による「正法」の額が掲げられた山門をくぐると、参道には見上げるばかりの大石垣が続きます。また、裏山の岩肌には県下では珍しい磨崖仏が彫られ、海抜500mの頂上近くには怪猫伝説を伝える八丈岩があります。
-
足助
宗恩寺
中馬の町並みを見下ろす高台に位置するこのお寺は、足助八景の一つ「宗恩寺の晩鐘」として綺麗な音色を街中に響きわたらせています。
-
足助
慶安寺
境内に当地方ではめずらしい、立派な弥勒菩薩の石像があります。 また門前付近には奈良町時代の須恵器が出土し、田町遺跡として知られています。
-
足助
三州しし森社中
猟師から仕入れた鹿&イノシシの角、骨、皮を活用したアクセサリーやクラフトが並ぶ、工房兼ギャラリー。 色や形の異なる鹿の角を使った、世界に一つだけのアクセサリー作りがお楽しみいただけます。 鹿は神の使いともいわれているので、お守りとして身につけるといいとされています。
-
足助
黍生城
平安末期、標高374メートルの山頂に、尾張国の山田重長が築いた山城です。 足助に居住後、足助氏を称し、以後、足助氏がこの地を治めるようになりました。 重長は足助氏の始祖とされています。
-
足助
地蔵公園
本町・紙屋裏に、平成6年に整備されました。土まんじゅうの上を拳大の川原石でおおった江戸時代初期のものと思われる墓があり、同中期に建てられたと思われる六地蔵や供養塔が祀られています。よく植栽が施され、付近を散策する人の休憩地ともなっています。
-
足助
足助城
真弓山(標高301m)にある足助城は、足助の町並みを見下ろすことができ、15世紀以降に西三河山間部に勢力を持っていた鈴木氏が築城したと考えられています。 1590年(天正18年)の家康の関東入国に従って関東に移ったため、廃城となりました。現在は城跡公園足助城として整備されており、高櫓・長屋・物見矢倉・厨(くりや)などの建物が復元されています。発掘調査成果に基づき「全国ではじめて復元された山城」です。
-
足助
伊勢神峠
旧東加茂郡と北設楽郡の境に位置する峠道(標高780m)。峠には中馬や善光寺参りの人々が往来した当時の道、明治30年(1897年)竣工の伊勢神旧トンネル、国道153号の昭和のトンネルがあり、3代にわたる道の歴史を見ることができます。なお、中馬街道の一部は、東海自然歩道となっており、峠には江戸時代末期に設けられた伊勢神宮の遥拝所があります(現在の遥拝所は再建されたもの)。ここからは伊勢湾一帯が一望でき、素晴らしい眺めを楽しめます。
-
足助
普光寺
「おびんずるさん」と呼ばれる賓頭尊者が祀ってあります。 賓頭尊者というのは、自分の痛いところと同じところを撫でてお祈りすると治るといわれています。また江戸末期に活躍した俳人・板倉塞馬の句碑と、黒炭の製法をこの地に伝えたということから、加茂黒炭の祖としてもしたわれ、その顕彰碑が建ってています。